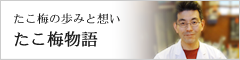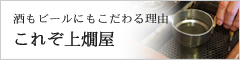たこ梅物語

今年で百七十年を迎えるおでん屋、
大阪でいうところの関東煮屋(かんとだきや)が道頓堀にある。
この界隈で、今や一軒だけになってしまった木造瓦葺き、昭和そのまんまの店。

軒先には、畳二畳はあろうかという海老茶地に
白く「たこ梅」と染め抜いた大きな暖簾が揺れている。
店の中に一歩足を踏み込むと、
コの地型で飴色になった檜のカウンター、
その真ん中には関東煮の大きな鍋が
これまたデンと構えている。
辺りを見渡すと、
錫のコップで燗酒をチビチビやる初老の男性、
タコを甘辛くたいたこの店の名物「たこ甘露煮」を
つまんでいる常連らしいお客、
もう、ほとんど見られなくなった鯨のサエズリや
コロの関東煮を満足げに堪能してる人もいる。
お父さん、お子さん、おじいちゃんと
三世代で飲んだり食べたりする家族、
酒を注ぎ合うカップル、取引先の話で夢中な上司と部下、、、
いずれも、楽しそうに酒を飲み、たこ甘露煮や関東煮を喰らい、語らっている。
この一見楽しく繁盛している風の店、
実は、五年もの間、店を閉め、倒産も覚悟した時代があった。
大阪の道頓堀で弘化元年、西暦で言うと一八四四年、
もうチョットわかりやすく言うと坂本龍馬が八歳、土佐でまだ寝小便を垂れていた頃、
魚のすり身を油で揚げる天ぷら屋の息子、梅次郎が、
たこ甘露煮と関東煮を喰わせて燗酒を飲ませる上燗屋「たこ梅」を始めた。

当時、店主が
カウンター越しにお客へ「ヘイヘイ」と
酒やアテを四方八方に手を伸ばして供する姿が
「蛸に似ている」ことからカウンターを
「たこ」呼んでいた。
それで、その「たこ」と「梅次郎」の一字をとって、
「たこ梅」と屋号にしたらしい。
たこ梅の初代梅次郎が独自に炊き方を工夫した
蛸とは思えない柔らかさの「たこ甘露煮」と、
鯨の舌に独特の加工を施した「サエズリ」の関東煮が評判を呼び、
明治四十五年発行の「近畿見物大阪之巻」に
挿絵付きで紹介されるくらい大繁盛だった。
順調に商売をしていたが、太平洋戦争が始まり、
昭和二十年三月の大阪大空襲で道頓堀界隈は焼け野原、
たこ梅も店を焼失。その時、三代目の松治郎は出汁だけ抱えて逃げたという。
その後しばらく、
堺筋から松屋町あたりまで転々とバラックでなんとか営業を続けた。

苦労の甲斐あって、
昭和二十四年に道頓堀の今の場所に店を構え、
三代目と跡取りの四代目正弘はともに商売に精を出した。
おかげで、店は盛り返し、
作家の池波正太郎さんや開高健さん、檀一雄さん、
田辺聖子さんら数多くの作家や文化人にも愛され、
その小説やエッセイに、たびたび登場するようになる。
そんな順風満帆のたこ梅の大きな悩み、
それは、跡取りとなる男の子がいなかったこと。

東京オリンピックの二年後、
三代目の三人いる娘のひとりに待望の男の子
「哲生」が生まれた。
子どもがなかった四代目の正弘は、特にかわいがって、
しょっちゅう車で店に連れていっては、
関東煮をくわせたり、小遣いをやっていた。
哲生の家は、
祖父母と店で働くお姉さんも何人か一緒に住む大家族。
その皆から、哲生はかわいがられた。
家は大阪市内の大和川のちょっと北側にあったが、
住み込み店員さんのひとり、カヨさんの弟が池田で農家をやっていて、
休みのたびに連れて行ってもらっては、
虫や魚を捕って自然の中を走り回る子に育った。

そのせいもあってか、生き物に興味を持ち、
コケを集めては図鑑で調べて分類したり、
魚も虫もやっぱり図鑑で調べては飼うのが趣味になった。
末は、「ダーウィン」のような博士になるのが夢だった。
そんな知的野生児とも言える哲生に、
ひとつの悩みがあった。
自宅に大きな釜があって、
名物の「たこ甘露煮」をたいていたのだが、
交代でたきに来る店の人の中には、子どもから見るとガサツで乱暴に見える人もいた。
周囲の店を継いで欲しいという期待とは裏腹に
「飲食業って、なんかいやや!」と思うようになっていったのだ。
そのせいか、大学は農学部に進み、バイオテクノロジーを専攻。
遺伝や培養を学び、食品と化粧品を扱うメーカーに入った。
希望したわけではなかったが、広告の部署に配属になり、
その後、マーケティング、ブランド開発を担当することになる。
子どもの頃から、見たことのないもの、珍しいもの、
新しい情報を収集しては分析するのが大好きだったから、
まったくもって初めてだらけの仕事に、
好奇心を大いに刺激され、どんどん吸収して楽しく働いていた。
その頃、三代目松治郎が亡くなり、道頓堀の本店は四代目正弘が、
梅田に出した三支店は長女宣子が継いでいた。
本店も梅田の三支店も高度成長からバブルの波に乗って絶好調。
しかし、バブル崩壊と時を同じくするように、本店では、四代目が亡くなり、
その妻珠恵が女将として本店を背負った。
しばらくして、梅田の支店を経営していた宣子も倒れ、
その親戚が経営に当たることに。
本店も支店もなんとかがんばったが、
平成七年の阪神淡路大震災をきっかけに経営が悪化、厳しい状態に陥った。
平成十三年、梅田の支店を経営していた宣子が亡くなり、
その息子哲生がメーカーを退職して家業に入った。
しかし、この時、本店も支店もすでに大きな赤字を出す状態で、
このままでは、二年以内に倒産というありさまだった。

それでも、代々受け継いできた本店だけは
なんとかそのまんまの姿で残したい!
売ったり、貸しビルにはできん!
なんとか手放さずに持ちこたえるには、、、
通常のやり方では到底不可能、
本店も支店も共倒れするのが関の山。
その時とった生き残りを掛けた捨て身の挑戦、それは、
一旦、最も経営の厳しかった本店を閉店、
売上が圧倒的に大きい梅田の支店をまず再生するというもの。
そこで、余力を蓄え、次ぎに、本店を再開再建するという大胆なものだった。
背に腹は代えられない。平成十四年七月、多くの人に惜しまれながら、
たこ梅と染め抜かれた大きな大きな暖簾が、
道頓堀のたこ梅本店の前から消えた。
いざ、梅田の支店の再生と意気込んではみたものの、
メーカー帰りの哲生にとって飲食業はずぶの素人、
店のスタッフはずっと年上の職人さんばかり。
ちょっとやそっとでは、うまくはいかない。
それでも、このままでは店がなくなるという危機感から、
メーカー時代に学んだマーケティング、製品管理、原価管理の手法を活用し、
粘り強く店の状況を説明しながら
スタッフの理解と協力と血のにじむような努力のおかげで、
とうとう数年後には黒字化を達成。さらに、売上も少しずつ増えていった。
よかった!少し蓄えもできてきた!
今なら、なんとか本店を再開できるかも!
平成十八年の初夏、哲生は、
腰を悪くして入院している本店の女将珠恵を訪ね、再開に向けて動き出した。

戦後の風雪に耐えてきた本店の建物は、
木造瓦葺きであちこち痛み、
このまんまでは、地震がきたらひとたまりも無い。
かといって、ビルにはしたくない。
つぶして建て直す方が簡単なのはわかっていたが、
先代、先々代の汗と想いの染みこんだ店を
なんとしても残したかった。
だから、お金も時間もかかっても、
一旦解体して耐震補強や補修、
元に戻すという道を選んだ。
暖簾にもこだわった。
たこ梅の暖簾は、日本橋一丁目の北浦染工場で、戦前から作ってもらっていたもの。
暖簾の「たこ梅」の文字も、代々の北浦さんの手で書かれていた。
哲生が暖簾を頼みに行ったら、北浦染工場の大将が、
「せっかくや、あんたが書いたらどうや?
あんたが書いたら、暖簾屋の字とちごうて、
世界で一個だけのたこ梅の字ぃができるで!」とけしかけられた。
「そんなん、筆なんて高校以来持ったことないし、、、」と躊躇すると
「大丈夫、千回書いてみぃ、見られる字ぃになるよって!やってみ!」
その足で書道の道具を一式買って、
毎日、毎日、仕事の合間に一時間以上書き続けた。
初めは、字が大きすぎて半紙からはみだしたり、墨がとびちって服はワヤになる。
もちろん、手は、真っ黒!それでも、一ヶ月くらいたつと、
「おっ!ちょっと、字ぃらしいなってきたで!」と思えて笑顔が出た。
二ヶ月目には、「整ってきたけど、もっと迫力いるな!」とか、
書きたい文字をイメージできるようになり、
もっといい字を、もっとたこ梅らしい字を書きたいという欲もでてきた。
書き続けること三ヶ月余り!千二百回以上書いたとき、
「うん、これならいける」と、北浦染め工場の大将のところへ持って行くと、
「よっしゃ、これでつくったる!」と、
大将が日焼けした顔をくちゃくちゃにして
二つ返事で受けてくれた。
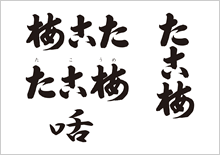
三ヶ月後、
哲生の想いと大将の腕と、
奥さんの縫いの技術が合わさった、
新しい門出を祝う暖簾ができあがった。
奥さんは、
「あんたが、昔と同じようにごつい帆布で
つくってくれ言うたから、縫うのも骨折れたわ!
せやけど、久しぶりに楽しかったで!」と
笑顔で店に暖簾を届けてくれた。
そして、平成十九年十一月、五年という苦難の日々を経て、
再び畳二畳はあろうかという大暖簾が店の前に掛かった。
「こんなに重いもんやったんや」・・・
哲生には、五代目として店を背負っていく責任の重さのようにも感じられた。
しかし、それは、再出発の快い重量感でもあった。
いいことは続くもので、ちょうどその頃、京阪電鉄さんから、
京橋に吉本興業の劇場が入るビルを建てるので
出店して欲しいとのお声をかけていただき、店を出すことに。
波に乗って、たこ梅が発展しようとしていたときだった。
しかし、平成二十年八月、リーマンショック!
一気に売上が下がり、オープンしたばかりの京橋の店も、
三ヶ月後には赤字に転落。やむなく、一年後には撤退。
平成二十一年十二月、木枯らしの吹く夜半過ぎ
「売上上げるんや!利益出すんや!って、ひたすら頑張ってきたけど、
売上下がる一方やし、あぁ~、どうしたらええねん、、、」
うなだれながら本店の暖簾をくぐると、カウンターに三人のお客さんが目に入った。
右に白髪まじりのお爺ちゃん、燗酒をチビチビのんではる。
左には、三十代後半のお父さんが、ジョッキでビールをグイッ。
その間では、小学校高学年くらいの男の子が、タコをモグモグ旨そうに食べてる。
その瞬間、哲生の脳裏に稲妻が走った。
「あ、この光景ってあれや! 見たことある!!」
哲生が小学生の頃、
本店に遊びに行くと四代目の叔父が、たこ甘露煮や関東煮を食べさせてくれながら、
「おい、テツ!うちの店はな、たこ甘露煮や関東煮、酒を売ってるだけちゃう。
うちのお客さんは、代々、お父さんがそのお子さん連れて来はる。
そのお子さんが大きゅうなったら、また、お子さん連れて来はるんや!
そうやって、三代、四代のお客さんが、ぎょうさんいてはる!
このカウンターで、親・子・孫さんが並んで楽しそうに食べて飲まはるんやで!」
と、繰り言のように言っていたあの光景や!

「そうや、これや!
これやからこそ、百年以上、続いてきたんや!
売上げちゃう!利益ちゃう!
こんな人と人が繋がれる場所、
親から子、子から孫へと
歴史を紡ぐ場所、つくりたいねん!!」
その時、哲生は決めた。
「自分が目指すたこ梅は、親子で来る、先輩後輩で来る、
並んでたこ甘露煮、関東煮 喰らいながら、笑顔で酒を呑む!!
酒が好きで、食べんのが好き、語らうのも好き、そんな人たちのオアシス!
友を繋ぎ、世代を繋ぎ、
人と人の歴史の縦糸、横糸を紡ぐ場所つくんのんが使命や!」って。
そうやって、百年後も、
今のお客さんのお子さんが、そのお子さんや友達つれて来てくれはる。
その友達が、その友達やお子さんを、、、
そうや、そんな、人と人の縦糸と横糸を紡ぐ場所になるんや。
僕だけやない、スタッフとスタッフを支えてくれはるご家族と、
取引先さんと、町の人と、もちろんお客さんと一緒に。
よっしゃ、やるでー!
百年後の僕の子孫、見とってくれよ。
ほんでな、次はあんたらの番やで。
次の百年に向かって、ちゃんとバトン渡したってや!